セクハラ・パワハラ行為者個別研修(加害者更生)プログラム
\超特急可!/
ハラスメント行為者の多くは、悪意ではなく、無知や認識の低さ、感覚のギャップ、勘違いなどにより加害行為をしているものです。
ゆえに、無知を知に、認識を更新し、一般的な感覚とのギャップを埋める指導を行うことが、再発防止策になります。
ただ加害者として罰するだけでなく、ハラスメントは人の生命、身体、権利、自由などを害するものであり、犯罪にもなり得る重大な問題であることに気づいてもらい、意識・認識・思考・行動の変容を促し、再発を防止する機会が必要です。
※カウンセリングや治療、人格変容は行いません。

資料ダウンロード
セクハラ・パワハラ行為者個別研修(加害者更生)プログラムについて詳しくご紹介しています。

無料ダウンロード(PDF)
(パスワード:harasserreha)
(2023年11月改定板)
※件数の多い企業様・機関様向け「顧問契約」もございます。
※パワハラ未満のパワハラ(不適切な指導等)にも対応しています。
セクハラ・パワハラ行為者個別研修(加害者更生)プログラムの重要性
セクハラ・パワハラ行為者個別研修(加害者更生)プログラムは、被害者及び職場のメンバーの安心・安全と、行為者自身の居場所を守るための支援です。
ハラスメント問題が発生し、事実確認調査を経て、被害者への対応と行為者(以下、「行為者」または「加害者」という。)の処分等が決定しても、その後も被害者と行為者は同じ組織で働き続ける可能性が高いため、関係改善に向けた取組が不可欠です。
また近年は、世代間ギャップに起因するハラスメントが増えています。行為者の若い頃は「むしろそうするべき」とされてきた言動が、現代では「むしろ不適切」とされてしまうのです。よかれと思っての行為でハラスメントと訴えられてしまうのは、本人にとって青天の霹靂で、やや気の毒に思えます。この世代間ギャップを埋め、現代の基準ではどのような言動が不適切でハラスメントに該当するのかを、教えてあげる機会が必要です。
会社としては、再発防止策の一環として、行為者への「教育」を行わなければなりません。
行為者への指導・教育は、被害者が再被害に遭ったり、新たな被害者が生まれたりすることを防ぐことに寄与します。
行為者にとっては、自身の行動・認識・意識・思考等を整理したうえで改め、信用と人間関係を回復し、居場所と未来を守るための「支援」「救済措置」となります。
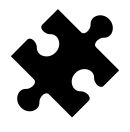
失ってしまった信頼を回復し、再び組織の中に「カチッと」居場所を取り戻すために、認識をアップデートするプログラム。
自覚と納得を促すために
行為者の多くは、無意識的に無自覚でハラスメント行為をしているもので、「加害者」とされても納得できず、行為者もまたメンタル不全に陥ります。
前述の世代間ギャップに起因するハラスメントは特に、モヤモヤが残るものです。
ただ「駄目」「加害者」とするだけでなく、「なぜ駄目なのか」を認識し納得したうえで、さらには「なぜその行為をしたのか」自身の心情・動機を深く掘り下げ、不適切性を自覚したうえでの、行動変容が必要です。
また、前提として、行為者からも行為の背景や弁明を十分に聞き取ることが不可欠です。
セクハラ・パワハラ加害者(行為者)更生個別研修プログラムは、行為者との個人面談によるヒアリングや相談対応、行為者への個別研修を実施する双方向対話型のサービスです。
セクハラ・パワハラ行為者個別研修(加害者更生)プログラムの必要性が増した背景
かつては、軽微なハラスメントは泣き寝入りされ、重大な事案のみが表面化していたため、加害者を解雇して終了となるケースが多くありました。
あるいは、労働者保護の意識が現在ほどは高くなかったため、就業規則の定めに関わらず、加害者を解雇してしまっていたケースもあったでしょう。
しかし現在は、「バカと言われた」などの、数年前までは問題にならなかったような被害の声も漏らさず拾われるようになったため、解雇未満の処分も増大し、被害者と行為者が同じ職場で働き続けるケースが多くなったことから、「加害者への指導・教育」の必要性が増しました。
以前
現在
当社のセクハラ・パワハラ行為者個別研修(加害者更生)プログラム
ケンズプロが実施する利点

独立性・客観性・中立性・専門性
ハラスメント事案が発生した企業様が自社内で教育を行うと、社員同士ゆえに、感情的になったり、真実を率直に話さなかったり、先入観を抱いたりするため、効果が半減、または逆効果になります。
当社が行うことにより、葛藤や心情を率直に語っていただくことや、先入観のない客観的な立場・視点による助言等が可能です。
専門的かつ柔軟でバランスの取れた、対話を取り入れたプログラムにより、「腹落ちする教育」を提供します。
超特急可
日程さえ合えば、初回または1回コースを最短で翌日に実施することが可能です。
- 実施までの手順を相当簡略化することにご了承いただける場合のみ超特急での実施が可能です。
- 日程が合わない場合も多くございます。必ず超特急で実施することをお約束することはできません。あらかじめごご承知おき願います。
- 担当者様からのZoom等による聞き取りの翌日以降となります。実施までの間に、受講対象者様に「事前チェックシート」をご記入・お送りいただきますので、タイトなスケジュールですがご協力をお願いいたします。
- Zoomでの実施となります。
- 一般的な内容になります。原則としてカスタマイズはできません。
臨機応変
内容や実施方法、オブザーブ参加等について、可能な限り依頼者様のご意向に沿い柔軟に対応いたします。
オンラインで全国対応
全回オンラインでの実施が可能です。
お客様の多くが全国・全世界に拠点を置かれる大企業様でいらっしゃることから、事案により地方に異動になった、本社以外の拠点で発生した、などのご事情が多いため、オンライン実施がお役に立っています。
※北海道札幌市にお越しいただける場合や、出張費及び日当等をご負担いただける場合は、対面での実施も可能です。
出張対応も可能
旅費交通費及び日当をご負担いただくことになりますが、一部の主要地域には出張も可能です。
交通費は、1回につき20,000円までは当社が負担いたします。
マンツーマン〜企業秘密の保護
完全に一社様に限定した個別指導のため、他社様に事案情報が漏洩するリスクがございません。
セクハラ案件にも対応
全国的に、「パワハラのプログラムはあるけれどもセクハラ案件に対応しているところがなくて…」と当社にお問い合わせいただくことが多くあります。
当社は、セクシュアルハラスメントやジェンダーハラスメントなど、特に男女間で発生しやすいトラブルについて研究を深めています。
男性へのセクハラや、マタハラやアカハラなど、様々なハラスメントにも対応しています。
実施形式
(1)個別研修プログラム
(2)社内指導サポート
(1)個別研修プログラム
プログラムの進め方(例)
ハラスメントは、人の生命、身体、権利、自由などを害するものであり、犯罪にもなり得る重大な問題であることを認識していただき、意識・認識・思考・行動の変容を促し、再発を防止します。
- ハラスメントに関する基本事項を確認し、自身の認識・行動と照合し「ズレ」への気づきを促す
- ハラスメントがもたらす負の影響を示し、重大性を諭し、自省を促す
- 良好な人間関係・信頼関係の構築に必要な心がけや効果的な手法を指導することにより、行為者の人間関係や信頼を回復し組織の中に行為者の居場所を守る
- 以上により再発を防ぎ組織及び組織のメンバーを守る
個別研修プログラムの進め方-1-1024x582.png)
※上プログラム例の場合、300,000円〜(+税)のお見積りとなります。
- お問い合わせ
- Zoom等によるサービスのご説明・担当者様からのヒアリング
- ご依頼の確定・ご契約
- 実施日の調整
- 必要に応じて担当者様からの詳細ヒアリング
- 事前チェックシートのご記入(受講対象者様)
- プログラムの実施
個別・オーダーメイド形式です。
発生した事案の内容、行為者の意識や性格、ご予算等により、内容、実施時間と回数、参加メンバー等を検討しご提案いたします。
実施が決まりましたら、日時を調整し、スタートします。
※上記1〜6を簡略化することにご協力いただける場合のみ、超特急での実施が可能です。
セルフチェックシート
プログラム開始前に、行為者様に、セルフチェックシートをご記入・ご提出いただきます。
ご自分でご自分の行為や動機を振り返り、また現在の心情や認識などを見つめていただくためのものです。
※メールフォームでご回答いただきます(Excelファイルでのご提出も可能です)。
第1回:ヒアリング(30〜60分間)
- 事前にご記入いただいたチェックシートに基づき、様々な角度から聞き取りを行います。
- 質問にお答えいただくことで、背景・問題点・抱負等をご自身で整理できます。
- 得た気づきを、以後実践していただきます。
- 第1回のヒアリング内容を、第2回以降の個別研修につなげます。
- 1回目はウォーミングアップです。当社とご本人との信頼関係構築を最優先とします。
ヒアリング項目例
- 当該行為の動機・背景
- 被害者の反応はどうだったか
- 行為者とされたことや処分されたこと、処分の重さなどに納得しているかどうか
- 現在の心情や考えていること
- 反省点
- 体調不良はないか
- 就業意欲や生産性の低下などはないか
- 信用回復に向けての抱負、等
第2回:個別研修による改善指導(約120分間)
第1回のヒアリングで把握した事案の背景や根本的原因に基づき、問題点を改善する「対話式」個別研修を実施し、行為者の認識・意識を刷新させます。
| ハラスメントに該当し得る行為 |
|---|
| ハラスメントの認識には個人差があるため、一般的な解釈の言語化・可視化により認識を標準化させる |
| 何が問題だったか |
| 今回の事案では何が問題だったのか(行為か、発言か、距離か、頻度か、立場を利用したことか、相手の被害の大きさか…)個別検証から問題点を指摘し、理解を促す |
| 行為者自身の内面的な問題点 |
| 被害者の心情や反応、被害者との関係性に関わらず、行為者側に何かの不足や歪みがなければ、ハラスメントは起こり得ない。行為者側の性格や気の緩み、その他動機など、原因・背景を深く掘り下げ、反省を促す |
| 被害者の心情と反応 |
| 一般的に被害者はどのような心情を抱きどのような反応をするか、多くは本心を隠し拒絶しないことなどを解説する。行為者が考える以上に、被害者にとってハラスメントは重大で深刻な問題であることの理解を促す |
| 被害者に起こり得る心身への影響 |
| 被害者は深く傷つき、心身の健康を害する。その害は一時的ではなく、長期間続くPTSDとなり得、最悪の場合は自殺もあり得る重大な問題であることを理解させる |
| 行為者自身や周囲への影響 |
| ハラスメントの害は、行為者自身や家族、関係者、同業者にも損害を与える。自分ひとりの問題ではない |
| 管理職としての心得 |
| ハラスメント上司は部下の心身に悪影響を及ぼし、成長を阻害し、飲酒や不眠症、自殺等の要因となり、人生を壊す。管理職には一般社員以上にハラスメントや人権について理解を深め、部下から尊敬され信頼されるよう心を磨き上げなければならないことの自覚を促す |
| 再発防止のための心がけ |
| コミュニケーションや指導における注意点、心がけを教示し、意識啓発を図る |
第3回:行為者プレゼンテーション+最終研修(90〜120分間)
最終回では、行為者様にプレゼンテーションを行っていただきます。
第2回までの進捗状況、理解度、改善度等により、内容や回数を組み立てます。
下は一例です。
※当社からの最終個別研修を実施することもあります。
レポート
以下の内容を含むレポートの発表により、プログラムの卒業宣誓をしていただきます。
- 本件の背景・原因
- 研修で得た気づき
- 再発防⽌と信頼回復のための抱負(⽅針・具体的⾏動等)、等
課題
事案の内容や行為者様の現状等により、テーマを決めて課題を出します。
例)
- チームの心理的安全性を高めるに何が必要か
- ハラスメント報道事例や判例をテーマとするケーススタディ
レポート提出
各回終了後、1週間程度を期限とし、気づきや、改善策、改善策を実践しての気づき、今後に向けてのコメントなどをご提出していただきます(行為者様のご様子やプログラムの進捗状況等により)。
報告書(当社から担当者様へ)
各回終了後、約1週間以内に、当社から、行為者様との対話を受けての所見や、今後の予定、助言等を、担当者様に提出いたします(Eメールにて)。
料金例
- 1回コース:150,000円〜(+税)
- 2回コース:200,000円〜(+税)
- 3回コース:300,000円〜(+税)
※上図「プログラム例」の場合(「担当者様からのヒアリング+プログラム全3回+担当者様へのご提案」の場合)、300,000円〜(+税)のお見積りとなります。
- 担当者様からのヒアリングと、終了後の担当者様へのご提案は、コースのカウントとは別に実施します(料金には既に含まれています)。
- 資料代は含まれています。
- 旅費交通費ほか、各種費用は別途ご負担いただきます(交通費は1回につき20,000円までは当社が負担します)。
- 同法人様で複数件(複数案件)ご利用いただく場合、2件目以降については割引がございます。
- 発生頻度高めの企業様・機関様向け年間契約(相談窓口セット)もございます。冒頭のダウンロード資料をご参照ください。
(2)社内指導サポート
社内担当者様による面談・指導への同席・助言
ご依頼企業様の人事担当者様など、社内の担当者様が指導面談される際に、オンラインまたは対面形式で同席したり録画映像を拝見したりして、必要な対応や再発防止策等を担当者様に助言する他、担当者様が個別研修を実施される際に、事前に内容や資料を拝見したり、研修等に同席または録画映像を拝見して事後アドバイスを行ったりします。
- 社内対応の流れ、方法、担当者選定等に関する事前相談/事後相談
- 行為者への指導面談への同席(オンライン/対面/録画映像視聴)
- 行為者への個別研修への同席・助言/内容企画・資料作成に関する助言
相談例
- このように社内で対応したいが、適切か、より良い方法はあるか?
- このように社内で対応したが、適切か、追加で実施すべきことはあるか?
- このように社内で対応したところ、このような結果になった。この後どうするべきか?
- 行為者に指導面談を行うので、同席して、事案の原因や本人の反省度、認識のずれなどを見て、今後の対応を提案してほしい。
- これから行為者に社内担当者がこのような内容で個別研修を行う。内容や資料についてアドバイスがほしい。
相談料例
1回 2時間程度まで 50,000円〜(+税)
- 旅費交通費ほか、各種費用は別途ご負担いただきます(交通費は1回につき20,000円までは当社が負担します)。
その他
1回のみ〜3回超も可能です
回数は、1回のみから3回超で調整できます。
顧問契約もございます
件数の多い企業様・機関様向け「定額制・顧問契約」もございます。
ご予算に合わせて組み立てます
回数、時間数、期間等を、ご予算に合わせて調整できます。
業務委託契約を締結します
原則として、2回以上のプログラムを委託される場合は、秘密保持条項を含む業務委託契約を締結します(電子契約)。
1回のみのプログラムでも締結可能です。
取り扱っているハラスメントの種類
下記は一例です。ハラスメントや人権、倫理全般を取り扱っています。
懲戒処分までは至らなかったケースや、ハラスメントに該当するとは言えないケースであっても、近年の考え方や風潮を「ご紹介する」研修を行うことでより良い方向へ導くことが可能です。
- パワーハラスメント(パワハラ)
- マイクロパワハラ(パワハラ未満のパワハラ)
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
- マタニティハラスメント(マタハラ)
- ケアハラスメント(ケアハラ)
- アカデミックハラスメント(アカハラ)
- 就活ハラスメント
- レイシャルハラスメント
- その他、ハラスメントやいじめ、人権侵害全般
受講者さまの実感
特徴
行為者を追い詰めるような「説教型」の指導ではなく、再発に注意しつつも組織で一層意欲的に働けるよう「前向きな指導」を心がけています。
【重要】ご留意いただきたい点
- 加害者の更生(再発しないこと)を約束するものではございません。
- カウンセリングや治療は行いません。人格や性癖を変えることはできません。
担当者

本プログラムは、代表の新田が担当いたします。
よくあるご質問
不祥事を起こした行為者たる社員に、費用をかけるべきでしょうか?
行為者への指導は、行為者のためでももちろんありますが、何より、その後も一緒に働くこととなる社員たちを守ること、ハラスメントにより低下した生産性を回復し、組織のパフォーマンスを高めることも目的です。ゆえに費用をかけることは、企業の利益に資することとなります。
オンラインによる受講でも効果はあるのでしょうか?
これまでの実績では、9割以上の受講者様にオンラインで対応し、期待以上の効果を得られたと評価をいただいています。直接対面方式の方がダイレクトに伝わるという利点は確かにございますが、オンラインで受講せざるを得ない対象者様や環境に、100%ではなくても不足なく適応できる柔軟性が求められるケースもございます。依頼者様の求める効果やご予算、ご事情に合わせ、臨機応変なスタイルで対応いたします。

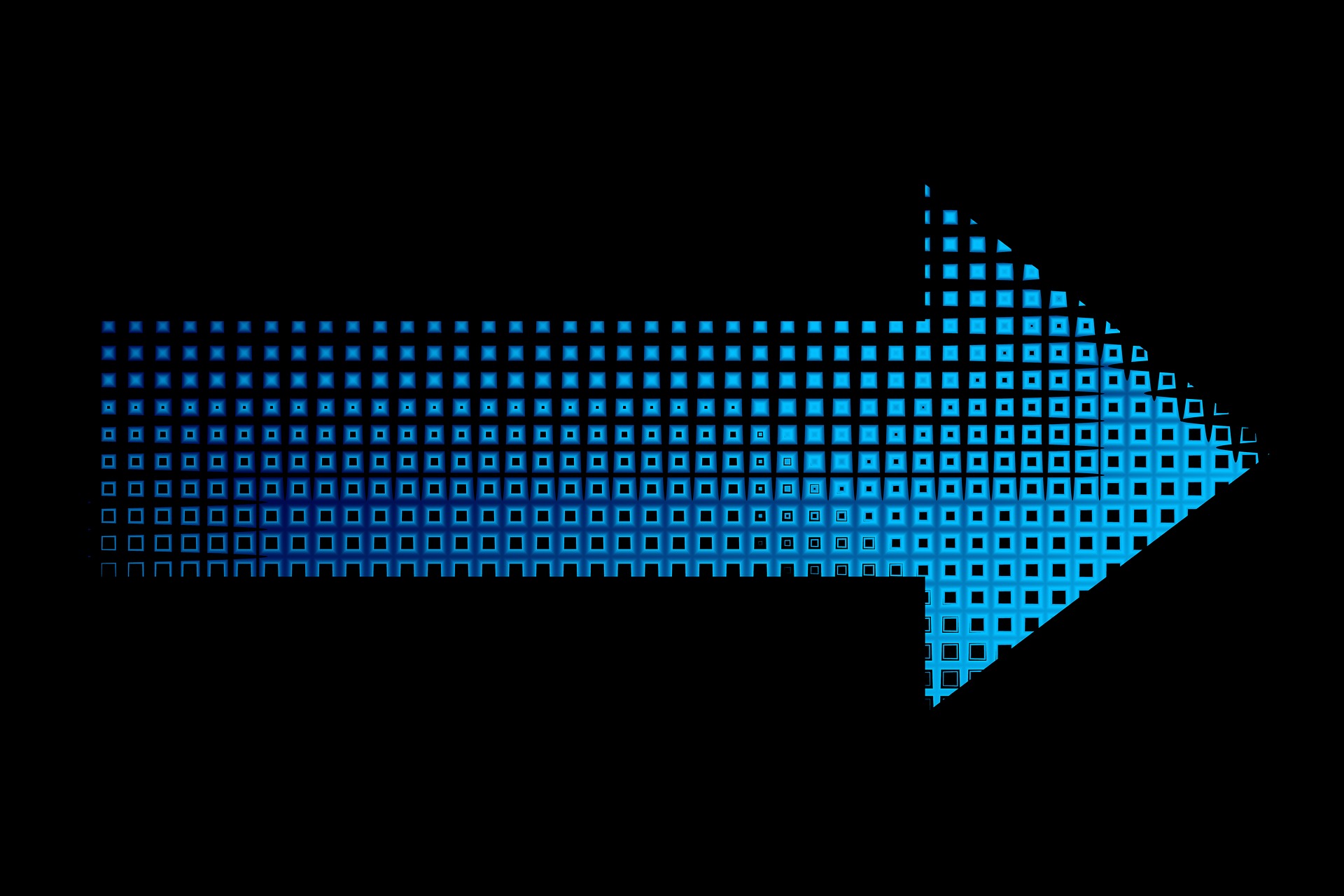

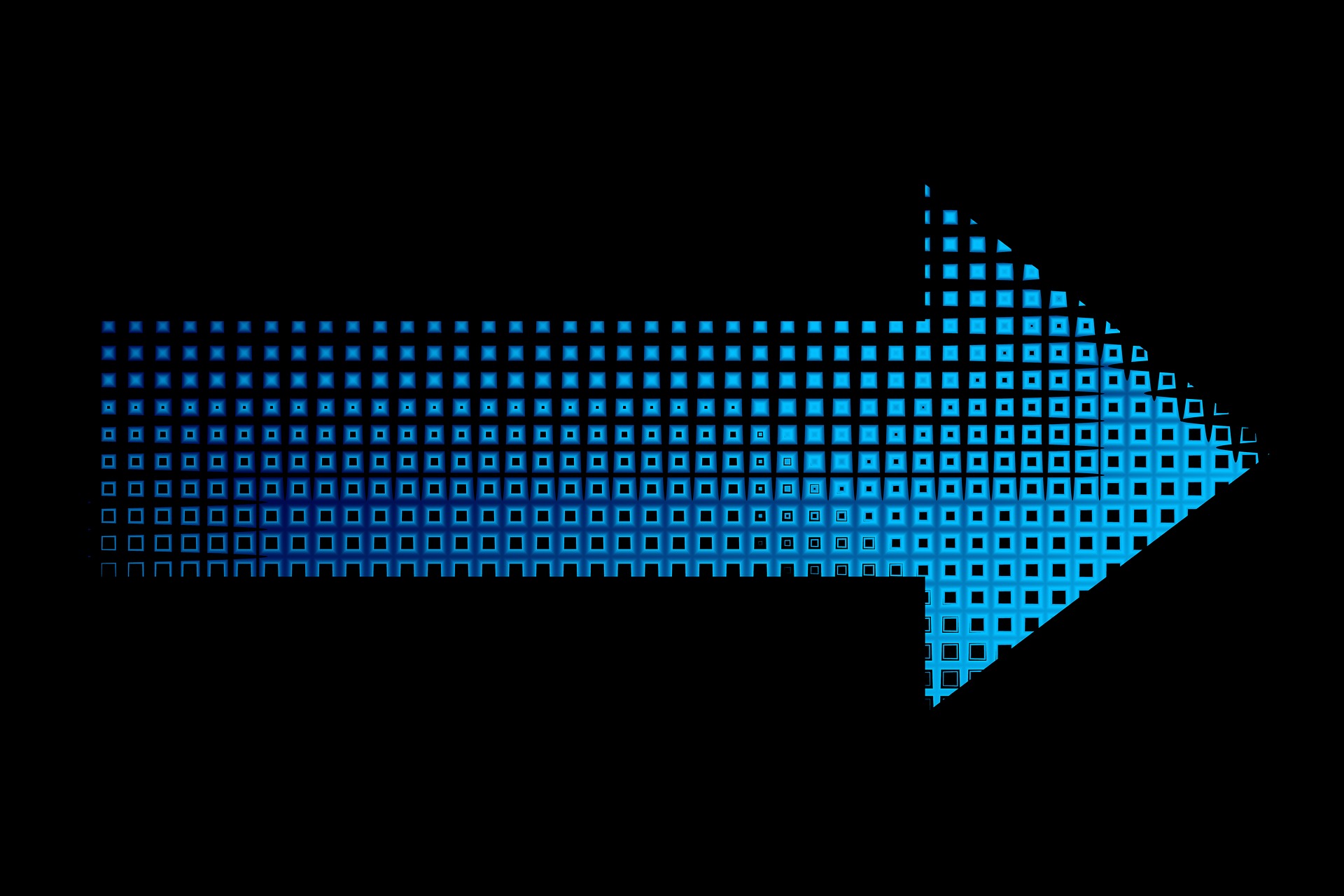
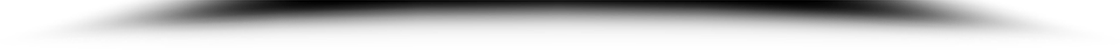
ハラスメント関連トピックス
- ハラスメント相談窓口<準備編> ハラスメント予防の基本のキ、「相談窓口」の利用を促進しましょう 4月 6, 2024
- 人事院が公務災害認定指針を一部改正、カスハラ等も対象に。 2月 19, 2024
- 福岡 宮若市長がパワハラ発言か 複数の職員が申し立て(2023年11月28日 NHKニュース) 11月 29, 2023
- 日大副学長、林理事長を提訴 辞任迫られたのは「パワハラ」と主張(2023年11月27日 朝日新聞DIGITAL) 11月 27, 2023
- 元教育実習生が千葉県を提訴 パワハラで就労不能に 「お前なんか教師になれない」指導担当の教員が暴言吐く(2023年11月6日 千葉日報) 11月 7, 2023
- ガールズケイリン「師匠」に賠償命令 セクハラ発言、女性選手が勝訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 30, 2023
- 残業代未払い・パワハラ、事務責任者ら処分 相撲協会(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023
- 山口大医学部でアカハラ、女性講師に労災認定 賠償求め大学を提訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023
- ハラスメント議員、公表します 自治体職員が被害、条例制定の動き(2023年9月23日 朝日新聞デジタル) 9月 23, 2023
- 韓国DJ SODAさんへのわいせつ行為とセカンドハラスメント 9月 19, 2023
- 少年らに性加害 50年間、「ジャニーズ」と似る―豪競馬界(2023年9月14日 時事通信) 9月 14, 2023
- 米タイム誌「次世代の100人」元陸上自衛官 五ノ井里奈さん選出(2023年9月14日 NHKニュース) 9月 14, 2023
- 日本ハム伊藤選手、誹謗中傷の被害。企業に求められる対策は? 9月 12, 2023
- 女子生徒抱きしめ、LINEで「かわいい」とメッセージ…セクハラで山口県立高教諭を停職(2023年9月9日 読売新聞オンライン) 9月 11, 2023
- 区立中学校校長逮捕 少女のわいせつ画像所持か 東京 練馬区(2023年9月11日 NHKニュース) 9月 11, 2023
- 石狩市議会議員 強制わいせつ容疑で書類送検(2023年9月11日 NHK北海道ニュースウェブ) 9月 11, 2023
- なぜ?「軽い冗談」「発言によるセクハラ」も放置してはならない理由 9月 10, 2023
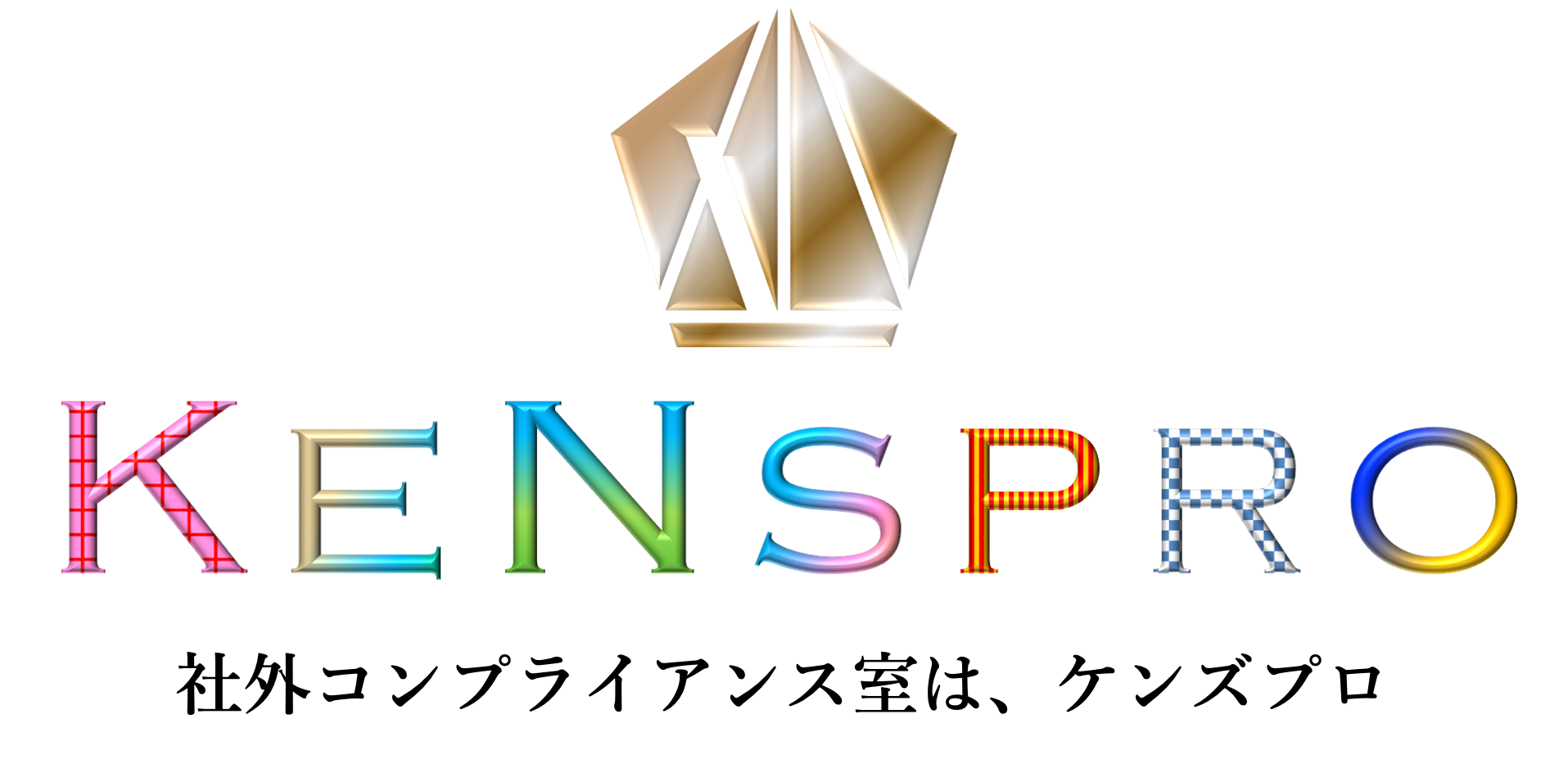
個別研修プログラムが必要な理由2.png)
個別研修プログラムが必要な理由3.png)