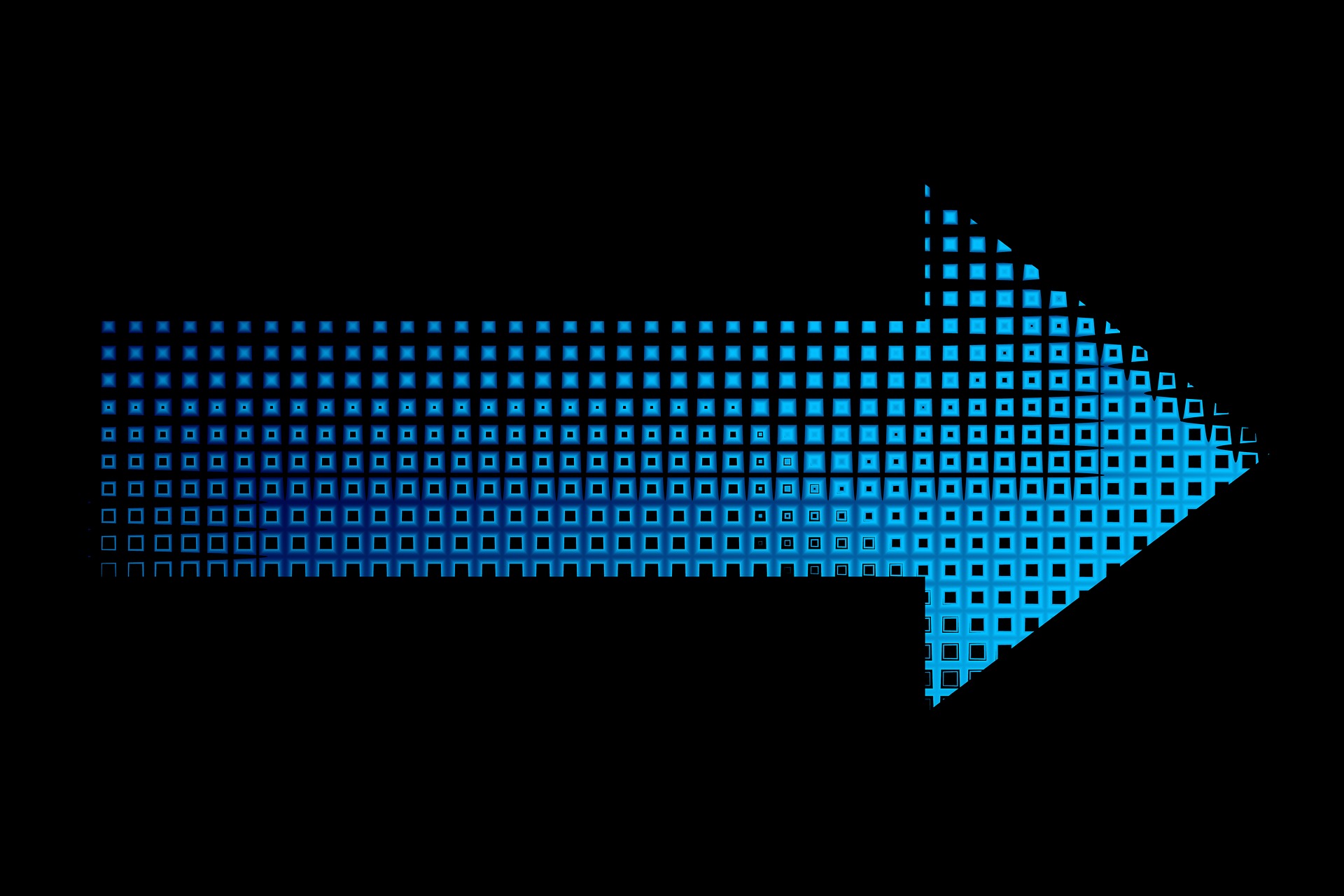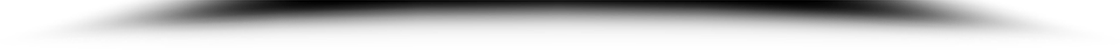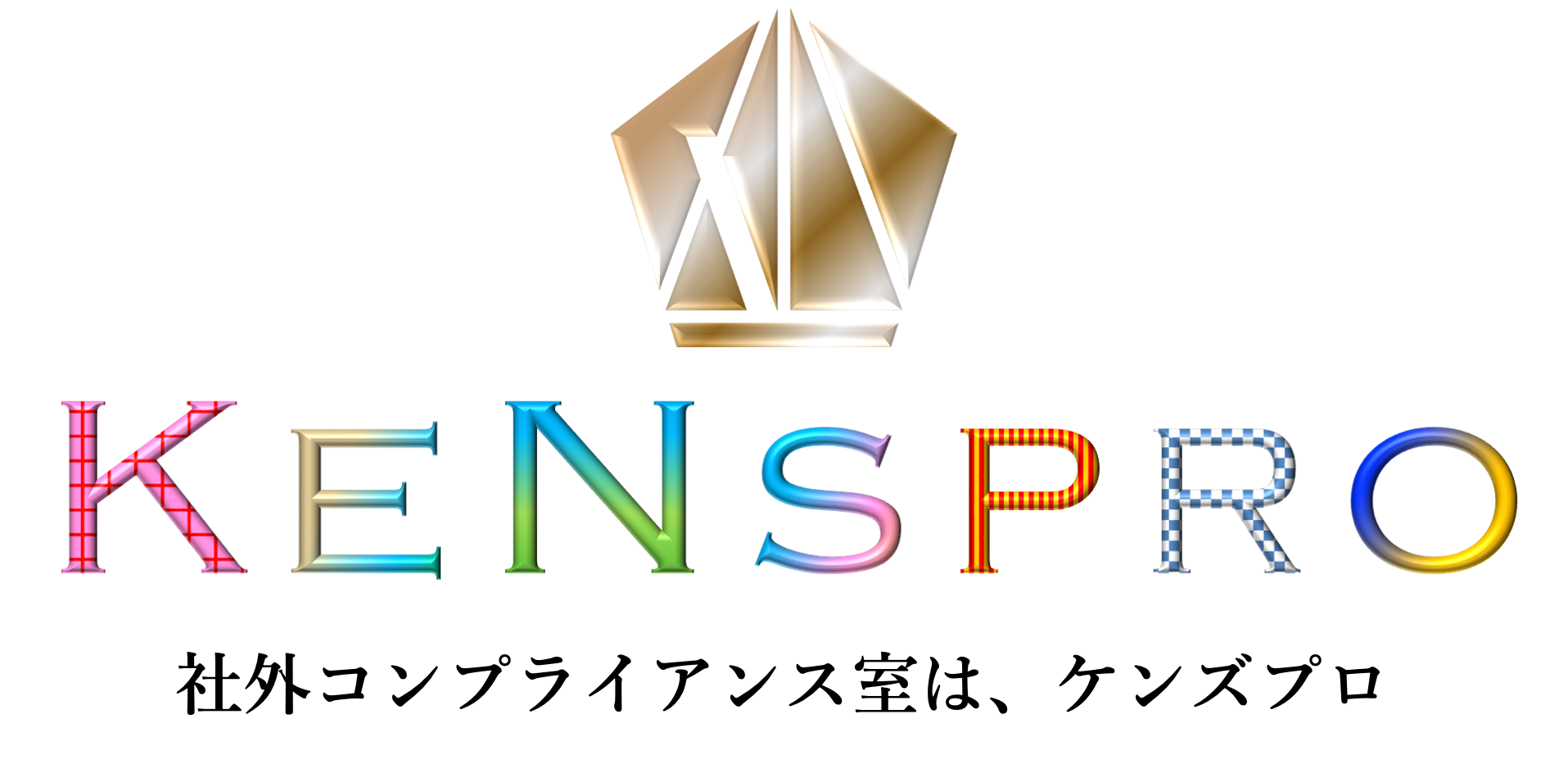ハラスメント防止規程・就業規則・ガイドラインの整備
ハラスメント防止規程や服務規律、懲罰規定がなければ、
発生時対応ができません!
労働基準法により、常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、個人・法人問わず就業規則を作成することが義務付けられています。
就業規則は、企業と社員の関係を律する大切なルールで、職場の憲法とも呼ばれています。
近年、社員によるSNSへの不適切投稿、不適切行為、不適切な休職、権利主張型社員の訴えなどが増え、経営までもが脅かされる事態が増えています。
また、ハラスメントや長時間労働、労働災害等の経営リスクも多様化しています。
企業を守るためのルール作りが急務です。
服務規律規定、罰則規定、退職規定、休職規定の他、安全管理規程、企業秘密保持規程、個人情報取扱規程、SNS運用規程などを明確に定めましょう。
また、万が一問題が生じたときや、その兆候に気づいた際も、担当者によってバラバラではなく、全職員が適切な対応を取れるように。
いざというときも慌てず、二次被害に拡大させることなく落ち着いて対応できるように。
対応マニュアルを定め、周知しておくことも重要です。
ハラスメント防止規程・就業規則他、当社のサポート
あらゆるルールの策定、文書化、効果的な運用をサポートします。
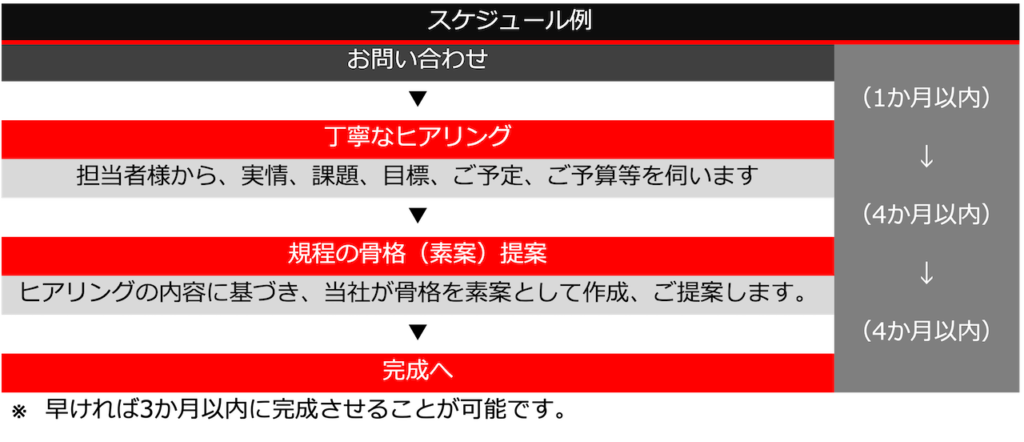
就業規則
- 就業規則
- 服務規律規定
- 懲戒規定
- 休職規定
- 退職規定
- SNS運用規程・ガイドライン
- ハラスメント防止規程
- 安全管理規程
- 育児・介護休業規程
- 賃金規程
- 退職金規程
- 役員規程
- 契約社員規程
- テレワーク勤務規程
- 企業秘密保持規程
- 個人情報取扱規程、等
ガイドライン・マニュアル等
- 各種ガイドライン
- 各種対応マニュアル、等
顧客/患者・利用者・家族への文書
- 利用規約
- 説明書
- 契約書
- 注意喚起ポスター、等
内部書式・文書
- インシデント・レポート
- 誓約書
- 雇用契約書、等

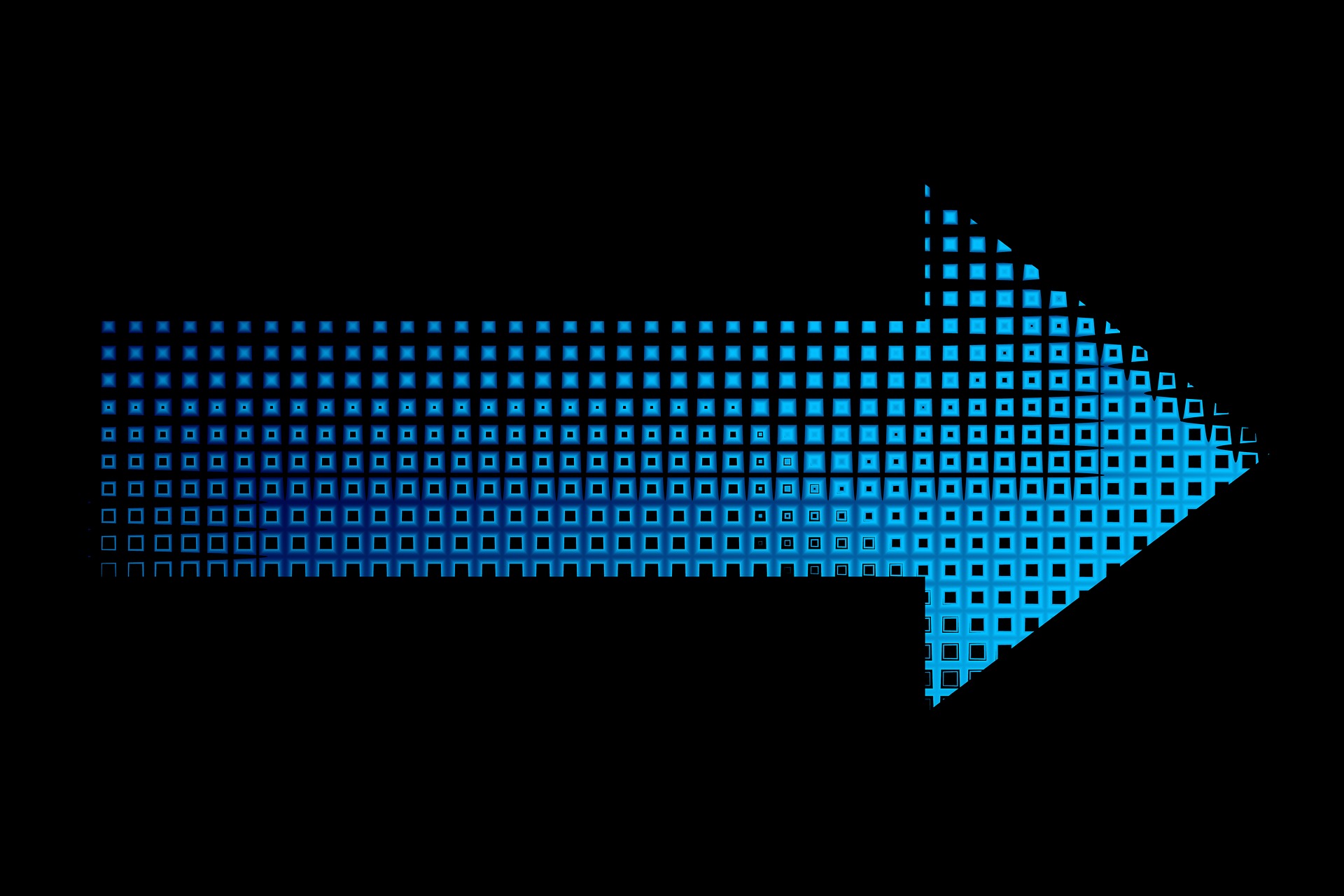
finger-2956974_1920
ケンズプロがサポートします
お問い合わせ・ご依頼・ご相談
technology-3378259_1920
料金表