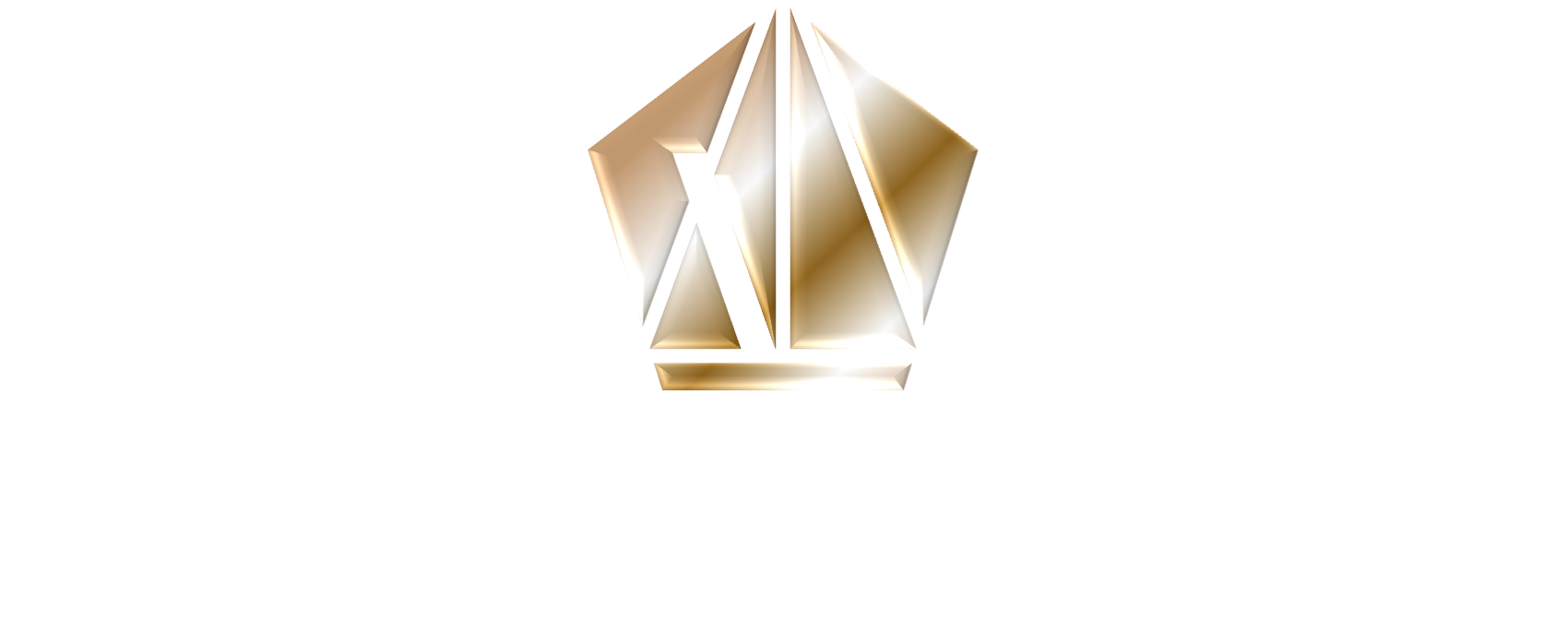「我社にセクハラはない」は、勘違い!?
「我社ではセクハラはほとんど起きていない。だからパワハラを中心とした研修をしてほしい」とご依頼いただくことが多いのですが、そうおっしゃった翌日にセクハラ問題が勃発したり、アンケートを実施すると予想を超える被害経験件数に驚愕したりするものです。
セクハラは、被害者が声を上げづらく、セクハラに対する意識には性別差・年代差があること、密室で起こりやすいことから周囲も気づきにくいため、水面下で被害が拡大し、あるとき突然表面化します。
すべての企業が、「水面下にはセクハラがある可能性が高い」ことを想定し、パワハラだけでなく、セクハラ研修にも十分な時間を割き、理解を深め意識を高めることが大切です。
セクハラ防止研修
セクハラ防止研修を通じて共通認識を持つことが大切
ハラスメントや倫理違反は、人それぞれで認識にギャップがあるために起きてしまうものです。
Aさんにとってはセクハラでも、Bさんにとってはコミュニケーションだったり、Cさんにとっては必要な指導でも、Dさんにとってはパワハラと感じられたり・・・
自分にとっての「常識」が他人にとっては「非常識」だったり・・・
こうしたズレを少しでも埋めるには、セクハラとは?してはいけない行為とは?加害行為をしたらどんな罰を受けるの?被害を受けたらどうすればいい?など、セクハラ防止研修を通じて認識を社内で共有しておくことが非常に重要で有効です。
距離感を意識する
他人との距離感をつかめずに、無意識的にセクハラをしてしまっているケースが多くあります。
人が触れられたくない、立ち入ってほしくないと感じるパーソナルスペースには、心理的にも、身体的にも踏み込まないことを、意識していただく研修をします。
セクハラは犯罪になる
セクハラという言葉は、「ちょっとした悪ふざけ」程度のニュアンスでとらえられがちですが、セクハラ行為には犯罪行為が含まれますし、場合によっては被害者の命に関わる重大な問題です。
その重大性を認識していただき、危機意識を高めていただく研修をします。
被害者の心情を理解する
事件発覚後、加害者の多くは「合意の上だった」「好意を持たれていると思っていた」「嫌がっていなかった」と主張します。
しかし被害者は、「抵抗できなかった」「拒絶したら解雇されると思った」と訴えるものです。
セクハラ被害を受けているとき、被害者がどのような心情で、その後どれほど苦しみ続けるのかを、知っていただく機会とします。
セカンドハラスメントを知る
セクハラ被害者に対する風当たりは強く、「被害者にも非がある」「自意識過剰」「いまさら問題にするな」「そんなことくらいで」等の心無い言葉が被害者を追い詰めます。
直接の加害者だけでなく、その問題に触れるすべての人が、セカンドハラスメントの加害者になり得ます。
被害者の声を封じてはならないことを、認識していただく研修とします。
セクハラ防止研修プログラム例
- セクハラとは
- セクハラによる影響(被害者・加害者・会社・組織)
- セクハラの加害者にならないために
- セクハラの被害を受けたら
- 職場でセクハラ問題が生じたら
- セクハラの相談を受けたら
セクハラ防止研修の料金・ご依頼等
- セクハラだけでなく、パワハラやマタハラ、ジェンハラなど、多様なハラスメントを組み合わせて研修することが可能です。
- 管理職・一般社員・人事担当者・新入社員等、対象者を属性別に区分して研修することが可能です。

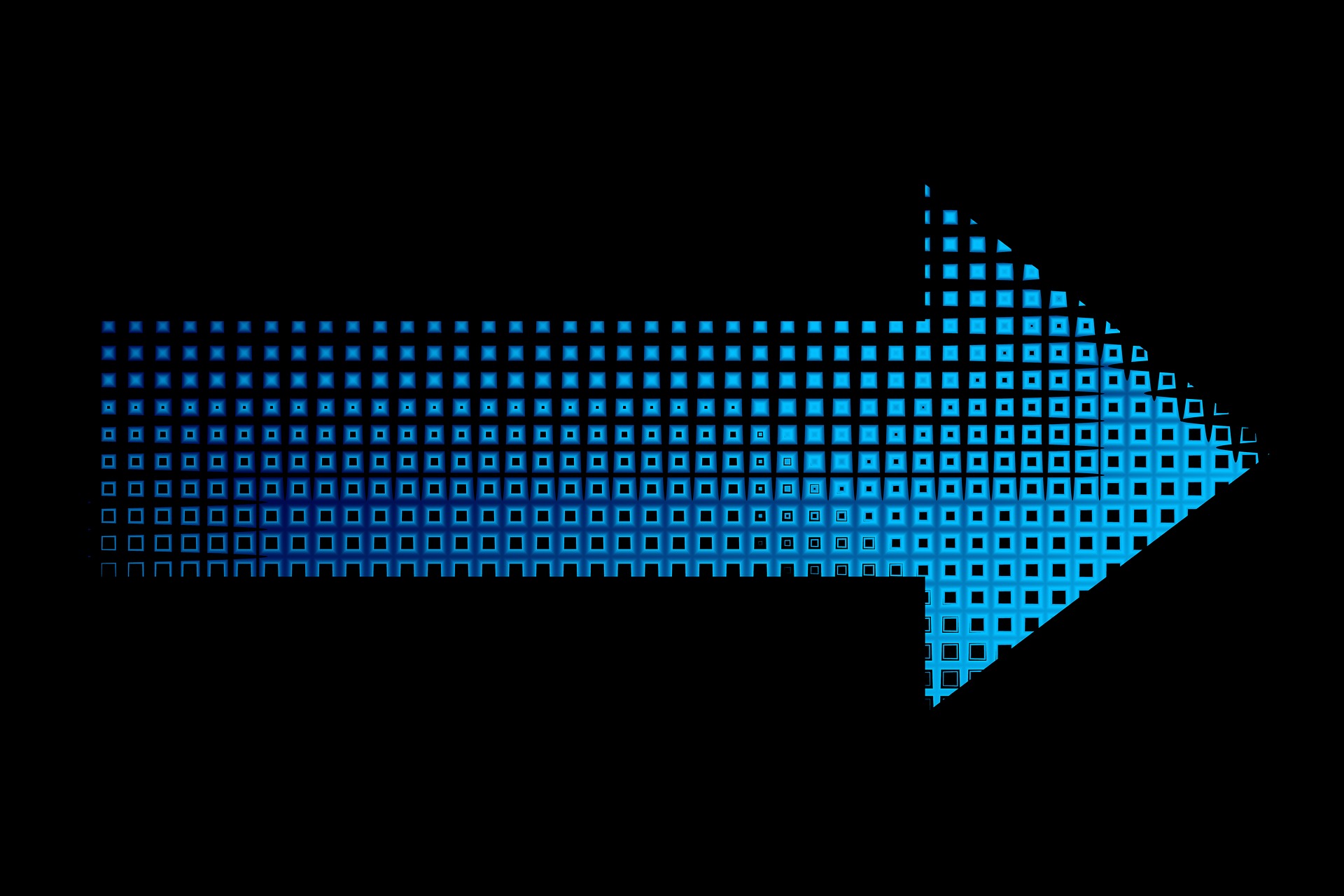

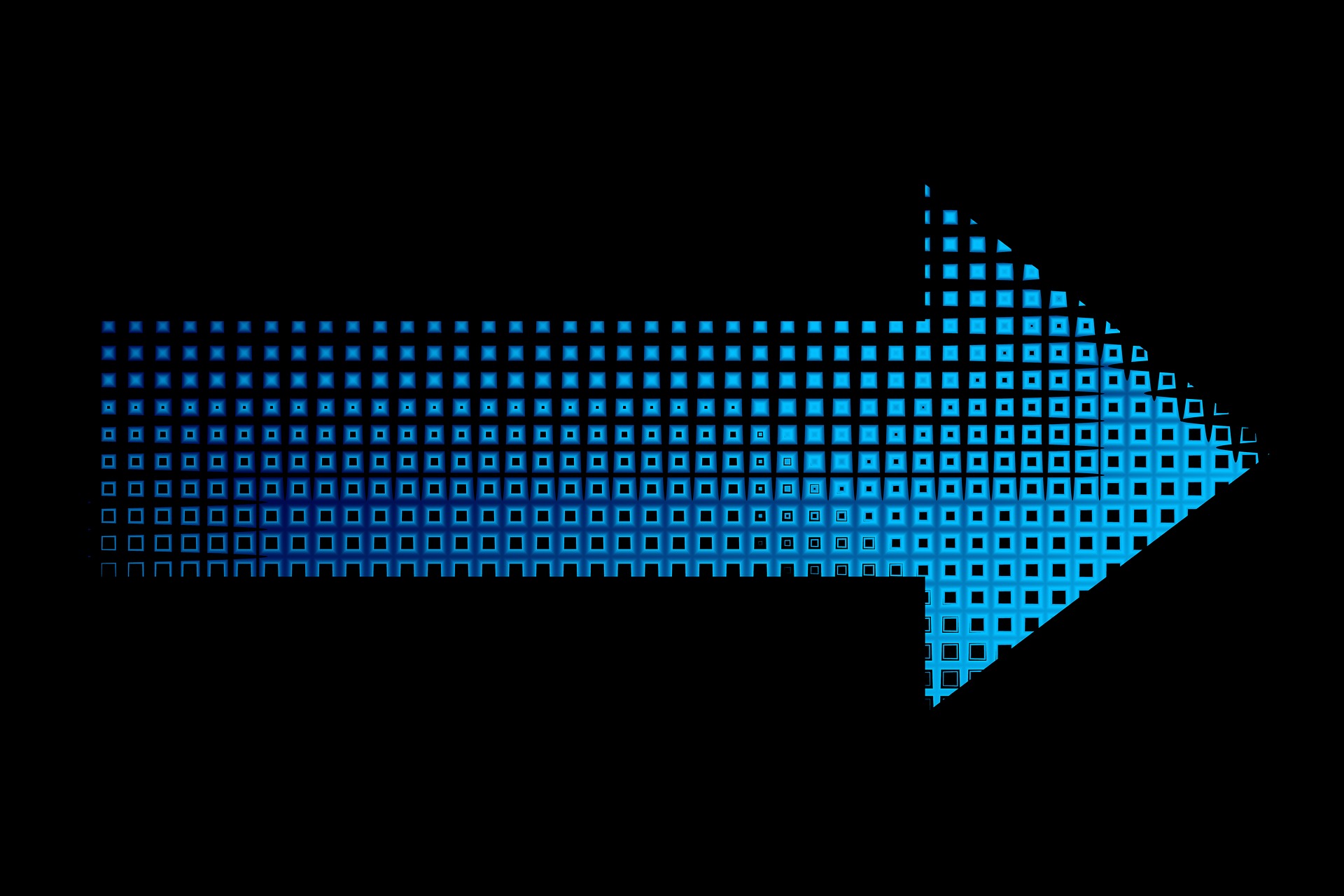
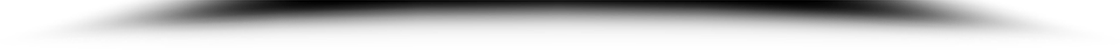
セクハラ関連トピックス
- ハラスメント対策、他社の取組状況は?〜厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査」から 6月 18, 2024
- 札幌国際大学様-ハラスメント相談担当者対象相談対応研修 5月 29, 2024
- 札幌国際大学様-アカデミックハラスメント等防止研修 5月 29, 2024
- 【ダウンロード】指導?パワハラ?チェックリスト 5月 29, 2024
- ハラスメント相談窓口<準備編> ハラスメント予防の基本のキ、「相談窓口」の利用を促進しましょう 4月 6, 2024
- 人事院が公務災害認定指針を一部改正、カスハラ等も対象に。 2月 19, 2024
- 福岡 宮若市長がパワハラ発言か 複数の職員が申し立て(2023年11月28日 NHKニュース) 11月 29, 2023
- 日大副学長、林理事長を提訴 辞任迫られたのは「パワハラ」と主張(2023年11月27日 朝日新聞DIGITAL) 11月 27, 2023
- 元教育実習生が千葉県を提訴 パワハラで就労不能に 「お前なんか教師になれない」指導担当の教員が暴言吐く(2023年11月6日 千葉日報) 11月 7, 2023
- ガールズケイリン「師匠」に賠償命令 セクハラ発言、女性選手が勝訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 30, 2023
- 残業代未払い・パワハラ、事務責任者ら処分 相撲協会(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023
- 山口大医学部でアカハラ、女性講師に労災認定 賠償求め大学を提訴(2023年9月29日 朝日新聞デジタル) 9月 29, 2023
- ハラスメント議員、公表します 自治体職員が被害、条例制定の動き(2023年9月23日 朝日新聞デジタル) 9月 23, 2023
- 少年らに性加害 50年間、「ジャニーズ」と似る―豪競馬界(2023年9月14日 時事通信) 9月 14, 2023
- 米タイム誌「次世代の100人」元陸上自衛官 五ノ井里奈さん選出(2023年9月14日 NHKニュース) 9月 14, 2023
- 女子生徒抱きしめ、LINEで「かわいい」とメッセージ…セクハラで山口県立高教諭を停職(2023年9月9日 読売新聞オンライン) 9月 11, 2023
- 区立中学校校長逮捕 少女のわいせつ画像所持か 東京 練馬区(2023年9月11日 NHKニュース) 9月 11, 2023