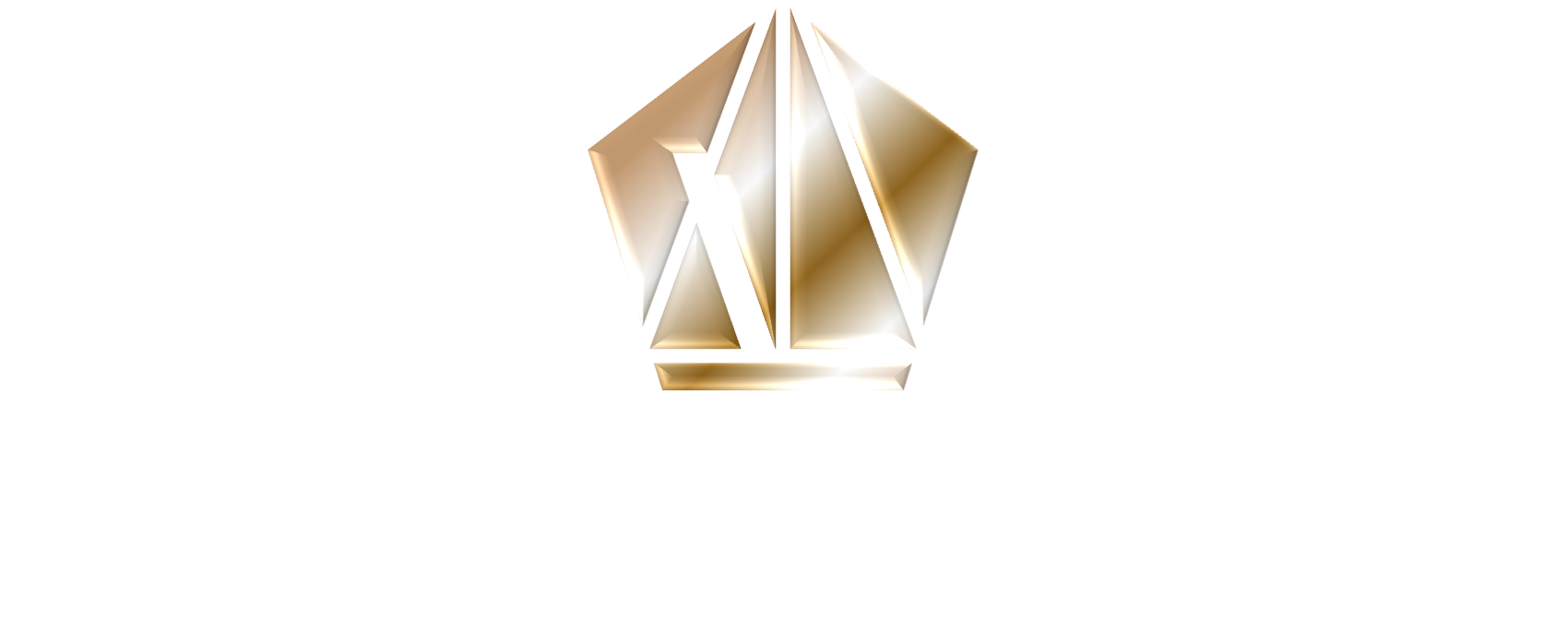ハラスメントは、被害者だけでなく、加害者の人生も破壊し、目撃者や同じ職場の仲間たちにも甚大なストレスをもたらし、会社全体を蝕む猛毒です。
被害者と加害者個人間の問題ではなく、企業の問題、組織の問題、みんなの問題です。
ハラスメントを目撃したら、見て見ぬふりをせず、可能な範囲内で構いませんので、誠実に対応することが大切です。
▼PDFダウンロード
Document「ハラスメントを目撃したら・仲間が被害を受けていたら」
投稿者

最新の投稿
- 2024年6月18日KEN's Noteハラスメント対策、他社の取組状況は?〜厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査」から
- 2024年5月29日アカデミックハラスメント札幌国際大学様-ハラスメント相談担当者対象相談対応研修
- 2024年5月29日アカデミックハラスメント札幌国際大学様-アカデミックハラスメント等防止研修
- 2024年5月29日パワーハラスメント【ダウンロード】指導?パワハラ?チェックリスト