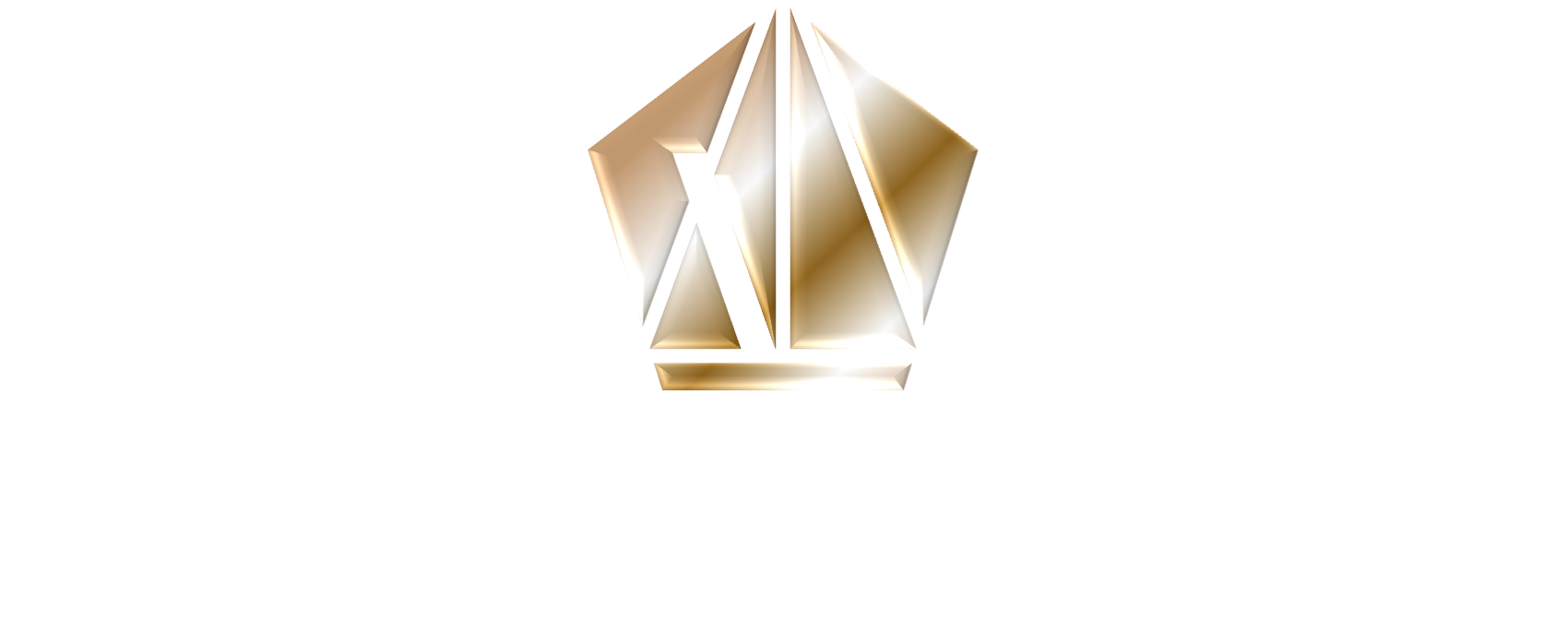ペイシェントハラスメントのページはこちら↓に移動しました。
関連ページ
- ペイシェントハラスメント
- ペイシェントハラスメントの行為事例
- ペイシェントハラスメントの発生要因と対策
- 医療安全管理指針の整備(ペイシェントハラスメント対策指針)
- 医療安全管理委員会の開催(ペイシェントハラスメント対策委員会)
- 医療安全管理研修の実施(ペイシェントハラスメント対策職員研修)
- ペイシェントハラスメント対応マニュアル作成
- ペイシェントハラスメント予防策(1)ー作業環境管理のリスク要因除去
- ペイシェントハラスメント予防策(2)ー防犯設備・システムの拡充
- ペイシェントハラスメント予防策(3)ー警備員の配置の充実・病院職員との連携促進等
- ペイシェントハラスメント発生時、被害者の対応
- ペイシェントハラスメント発生時、同僚等の対応
- ペイシェントハラスメント発生時、管理者の対応
- ペイシェントハラスメント発生後、職員のケアと被害者への対応
- ペイシェントハラスメント発生後、加害者への対応
- ペイシェントハラスメント発生後、組織的な対応・再発防止策の検討
- 【医療・介護】ペイシェントハラスメント予防・対応研修
- 【ダウンロード】ペイシェントハラスメント発生リスク・予防策チェックリスト